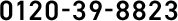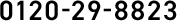将来に備える!50代から考えるバリアフリーリフォームのすすめ
- リフォーム基礎知識

- リフォーム基礎知識
バリアフリーリフォームは、介護が必要な高齢者や障害者のために住環境を整える重要な手段です。
現在介護を必要とする家族がいなくても、将来的なことを考え、体が元気なうちにバリアフリーリフォームをされる方も少なくありません。
この記事では、バリアフリーリフォームを実施することで、どのように介護が楽になるか、またどのようなリフォームにすれば良いかについて解説していきます。
バリアフリーリフォームの必要性
日本の高齢化は進行しており、多くの家庭で高齢者や障害者を介護する必要があります。
バリアフリーリフォームは、こうした状況において非常に重要です。
また、いざ介護が必要になってからリフォームをすると、騒音やスケジュールの調整等でリフォームがスムーズにいかないことも考えられます。
そのため、家族が元気なうちに早めにバリアフリーリフォームを検討するのが良いでしょう。
まずは生活の質を向上させるために、高齢者や障害者が自立した生活を送りやすい環境が求められます。
さらに、介護者の負担軽減も大きなポイントです。
バリアフリーリフォームを行うことで、介護者が高齢者や障害者の安全を確認しやすくなり、負担が軽減されることが期待されます。
経済的な側面から見ると、リフォームにかかる費用や手間は大きいですが、国や自治体から提供される補助金や減税制度を利用すれば、経済的な負担を軽減することが可能です。
バリアフリーリフォームを検討する際は、お住まいの自治体などで補助金などがないかも併せて確認しましょう。
自宅のバリアフリーチェックポイント
バリアフリーリフォームを成功させるためには、まず自宅の現状を正確に把握することが重要です。
バリアフリーリフォームのポイント
- 段差やステップの有無・・・高齢者にとって、少しの段差も大きな障壁となることもあります。玄関、浴室などの段差解消を検討しましょう。
- 手すりの必要箇所・・・階段、トイレ、浴室など、転倒のリスクが高い場所には手すりの設置はかかせません。設置してある場合でも、年数が経っている場合は取り換えを検討しでも良いでしょう。
- 床の滑りやすさ・・・年数が経っている住宅の場合、床が滑りやすくなっている箇所もあります。滑り止め加工を施した床材に交換する等、介護スペースだけでも床の張り替えを行うことで、安全性を向上させることができます。
- 生活同線の確認・・・日常的に利用する移動経路は、特にバリアフリー化を優先的に行う必要があります。例えば、車いすが十分に通れるスペースか、難しそうであれば廊下の拡張なども相談すると良いでしょう。
また、福祉住環境コーディネーターの資格を持っている担当者がいるリフォーム会社ですと、より具体的なアドバイスをもらいながらバリアフリーリフォームの相談をすることができます。
家族全員の安全と快適な暮らしを考慮して、自宅の現状をきちんと確認しましょう。
バリアフリーリフォームの施工内容
バリアフリーリフォームを行う際には、住環境を改善するための具体的な施工内容を理解しておくことが重要です。
先ほども述べたように、ひとえにバリアフリーといっても、様々な施工内容があるため、必要なリフォームを見極めて行う必要があります。
手すりの設置や段差解消など、具体的にどのようなメリットがあり、重要度が高いのか、詳しく解説していきたいと思います。
手すりの設置
手すりの設置は、バリアフリーリフォームの基本的な施策の一つであり、特に高齢者や介護が必要な方々にとって重要な役割を果たします。
玄関や廊下、階段、浴室など、日常生活で頻繁に利用する場所に手すりを設置することで、転倒や滑りを防ぎ、安全に移動できるようになります。
例えば、階段に手すりを設置することで、上り下りの際にバランスを取りやすくなり、転倒リスクが大幅に減少します。
また、浴室に設置された手すりは、濡れた床でもつかまりやすく、安全に入浴する助けとなります。
さらに、手すりの種類や素材にも注意が必要です。
握りやすい形状や滑りにくい素材を選ぶことで、より効果的な安全対策が可能となります。
段差の解消とスロープの設置
段差の解消とスロープの設置は、バリアフリーリフォームにおいて非常に重要です。
高齢者や障害者にとって、わずかな段差でも大きな障害となり転倒のリスクが高まります。
ケガを防ぐために、まずは自宅内外の段差を確認し、それを解消することが必要です。
例えば、現在玄関に入るまでに階段がある場合は、スロープを設置することで解決できます。
スロープは車椅子での移動が容易になる他、歩行が困難な方がスムーズに移動できるようになり、踏み外しによる転倒事故も防ぐことができます。
家の作りや条件によっては、スロープを設置するのが難しい場合もありますので、業者による現地調査でよく相談していただくことがポイントです。
滑り止めの床材
滑りやすい床は転倒のリスクを高めるため、住環境を安全に保つためには滑り止め機能が求められます。
ある程度年数が経っている住宅の場合、フローリングの表面が摩擦により滑りやすくなっていることも珍しくありません。
靴下やスリッパによっては滑りやすくなってしまうため、床材を交換する、また可能であれば滑り止めの床材を選ぶとより安心です。
滑り止めの床材には、シリコンやゴム、特殊な表面加工が施されているものなど、さまざまな種類があります。
具体的には、浴室やキッチン、廊下などで使用することが多く、水濡れや油分で滑りやすくなる場所には特に効果的です。
また、滑り止め床材には防水性や耐久性が求められるため、購入時にはそれらの要素もしっかり確認することが重要です。
万が一の転倒に備えたい場合は、クッションフローリングといったクッション性のある床材を選ぶと安心です。
車椅子対応の改修
車椅子対応の改修を行うことで、移動に不自由のある方や高齢者が安全かつ快適に生活できる住環境が実現できます。
まず、玄関や廊下、部屋間の扉を車椅子が通りやすくするために、幅を広げることが重要です。
室内のドアについても、開閉が容易で車いすユーザーでも通りやすい、引き戸へのリフォームも検討してみてください。
水廻りの設備については、浴室・トイレではフラットな床材や手すりの設置、洗い場の広さ確保がポイントになります。
また、多くの住宅の場合、靴を脱いでからあがる段差があります。
車椅子を使用する場合、この部分の改修も避けては通れなくなりますが、リフォームが難しい場合はステップなどを購入することで解消できます。
費用と補助金・減税制度
バリアフリーリフォームにかかる費用は、施行内容や住宅の状況によって異なりますが、一般的には数十万円から数百万円がかかります。
国や自治体は、高齢者や障害者のための住環境改善を推進しており、さまざまな支援策を提供しています。
例えば、介護保険を利用したリフォームでは、要介護認定を受けている場合に工事費の一部が給付されます。
また、自治体ごとに異なる補助金制度もあり、手すりの設置やスロープの導入など必要な改修に対して、費用の一部が補助されることがあります。
さらに、減税制度を利用することで、所得税の控除や固定資産税の減免が受けられる場合もあります。
こうした支援策を上手に活用することで、経済的な負担を軽減しながら、安心してバリアフリーリフォームを進めることが可能です。
補助金や減税制度の詳細は、自治体の担当窓口やインターネットで確認することが大切です。
それぞれの制度の条件や申請方法を把握し、計画的にリフォームを進めましょう。
バリアフリーリフォームをする際の注意点
バリアフリーリフォームを成功させるためには、いくつかの重要な注意点があります。
まず、家族全員が納得するリフォーム計画を立てることが大切です。
高齢者や介護者が使いやすい設計を考える一方で、家族全体の生活動線にも配慮しましょう。
次に、信頼できるリフォーム業者を選ぶことも重要です。
業者選びに際しては、過去の実績や口コミを参考にして、適正な価格で高品質なサービスを提供してくれる業者を選びます。
また、福祉住環境コーディネーターの資格を持つスタッフがいる業者だと、より専門的なアドバイスを受けながら相談することが可能です。
介護が楽になるためのバリアフリーリフォームで、老後も安心
バリアフリーリフォームは、介護を必要とする家族の生活を大きく改善する方法です。
住まいを改善することで、転倒やケガのリスクを減らし、介護者と高齢者双方の負担を軽減することができます。
また、介護保険や国・自治体の補助金制度を活用することで、経済的な負担を軽減することも可能です。
前もってしっかりと準備と計画を立てることで、安心して介護生活を送ることができるでしょう。
千葉建設工業は、福祉住環境コーディネーターの有資格者が在籍しています!
バリアフリーリフォームについて相談したい方は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。